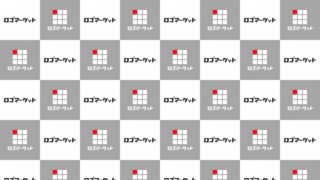ステッカーにロゴマークを印刷し、ノベルティとして配る企業を見かけます。
ロゴマークをステッカーにすることで得られるメリットは数多くありますが、場合によっては無駄になってしまうことも。
今回はロゴマークステッカーを作る本来のメリットを押さえた上で、無駄になる会社の共通点を3つご紹介します。
目次
ロゴマークステッカーの本来のメリット
ロゴマークをステッカーにした場合のメリットは、大きくふたつあります。
1.広告媒体にできる
2.印象に残りやすい
1.広告媒体にできる
ロゴマークは「会社を表すもの」であり、それ自体が広告媒体となるものですが、認知してもらわなければ意味がありません。
その点ロゴマークをステッカーにしておけば、展示会やセミナーなどで配ることができ、来場者に認知してもらうことができます。
ステッカーの場合、他のノベルティやパンフレットよりも小さいことがほとんどなので、かさばりにくく、持ち運びやすいのが特徴です。
そのため気軽に渡すことができます。
またステッカーには「貼ったものを広告として利用できる」というメリットも。
企業ステッカーをパソコンに貼っている人を見たことがあるかもしれませんが、目につく場所に貼ってもらうことで、直接接点のない人の目に触れる機会は格段に多くなります。
特に、自社と良好な関係を築いてくれている企業は、パソコンなどにステッカーを貼ってくれることが多いため、結果として第三者への広告媒体担ってくれることが多いのです。
接点のない人との接点が作れるという意味でも、ステッカーは広告媒体として大きな役目を果たしているといえるでしょう。
2.印象に残りやすい
パンフレットやPOPなどに比べ、ステッカーは情報量が絞られています。
多くの企業のロゴステッカーを見てみても、ロゴのみ、もしくは会社名とロゴのみ、というものがほとんど。
情報量が絞られている分、相手への印象はより強くなるため、覚えてもらいやすいのです。
特にデザインや色合いが印象的なものは、目に付きやすいという特徴もあります。
こうした理由から、IT企業などを中心に、ロゴマークをステッカーにする企業は少なくありません。
以下ではロゴをステッカーにしてくれるサービスをご紹介しています。
こちらもぜひ参考にしてみてください。

ロゴマークステッカーがムダになる会社の共通点とは?
さまざまなメリットがあるロゴマークステッカーですが、実は作っても無駄になってしまう可能性が高い会社もあります。
ここでは無駄にしてしまいがちな会社の特徴を3つご紹介します。
ロゴが社員に愛されていない
そもそも自社の社員から不評だったり、よく知られていなかったりすると、ロゴマークステッカーを配るという機運が起こりにくくなります。
社員から不評だと、たとえイベントでも「恥ずかしいから配りたくない」「もらってくれなさそうだから配らない」といったことになりかねません。
結果、パンフレットやPOPなど別の媒体が利用され、ステッカーが陽の目に出にくい、ということはあるでしょう。
また「会社のロゴマークを知らない人はいないだろう」という方がいらっしゃるかもしれませんが、実は「ロゴマークを知っている」だけでは「よくわかっている」とは言えません。
ロゴマークは成り立ちや意味を理解していて、初めて「よくわかっている」といえます。
こうした背景を理解していないと、お客様から「なぜこのロゴマークになったの?」と聞かれた時に、うまく答えられずに恥ずかしい思いをする可能性が。
「誰でも答えられる」と胸を張っていえない場合は、まず社員にロゴマークの成り立ちをしっかり理解してもらうことから始めたほうがいいでしょう。
イベントに出展することがない
イベントはノベルティなどを渡す機会が多く、また出展企業が数多ある中で差別化を図りやすいアイテムとしてロゴマークを利用しやすいというメリットがあります。
そのためロゴマークステッカーを配りやすいという特徴がありますが、それほど出展する機会がないのであれば、宝の持ち腐れとなるかもしれません。
会社ヘの来客が少ない
イベント出展同様に、来客されたお客様へ手渡すというのも、ロゴマークステッカーを配布する有数の機会です。
しかし、そもそも来客が少ないと、ステッカーを渡す場面も少なくなってしまうでしょう。
イベント出展が少ない、もしくは来客が少ない場合でもステッカーを作りたい場合は、小ロットで作成してみて、どれくらいで在庫がなくなるか確認した上で増量発注を掛けたほうが安心です。
ロゴマークステッカーがムダになる会社3つのの共通点 まとめ
ロゴマークの認知を広げられたり、相手に強い印象を与えやすいロゴマークステッカー。
しかし、会社の状況によっては制作費用が無駄になってしまったり、在庫が負担になることもあります。
今回ご紹介した「ロゴマークステッカーがムダになる会社の共通点」を確認した上で、自社にどれくらい必要なのかを見極めてみてはいかがでしょうか。