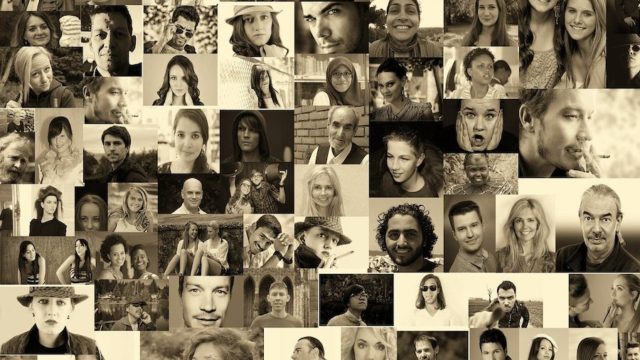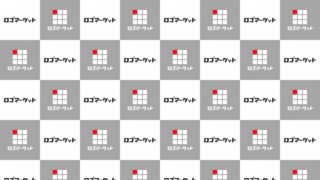私たちの生活の中でもよく聞かれるようになった「AI」という言葉。
エアコンなどの生活家電やコンピューターゲームの中で使われているほかに、ビジネスの場においては、簡単な事務処理などが段階的にAIへ変わりつつあるようです。
実はデザインの分野においても、AIが活用されているのをご存知ですか?
今回はAIができることとできないこと、そしてAIが作るデザインについてご紹介します。
目次
AIのできること できないこと
ここではデザインの分野において、AIのできることととできないことをご紹介しましょう。
「AI」という言葉は1956年に誕生し、およそ60年経った今、第3次AIブームに突入していると言われています。
AIの歴史はおよそ60年とまだ浅いものの、その進化から、AIであれば何でもできるだろうと思っている方が多いかもしれません。
しかしAIであっても、まだできないことはあります。
AIができること
AIはカメラやセンサーなどの機械の目で見た物体や背景を、ある程度人間と同じように判断することができます。
その上でできることは、以下に挙げる4点です。
- どこに何があるのかを識別する
- 機械の目で見た状況を言葉で説明する
- 機械の目で見た状況から専門的な判断を下す
- モノクロ画像をカラー画像にする
- 解像度の低い画像からでもものの形などを推定する
AIができないこと
デザインの世界に限りませんが、現段階においてAIにできないことはまだあります。
人間と同じように行うことができない点は以下に挙げる2点です。
- クリエイティブに動くこと
- 心を通じたやりとりをすること
AIを活用したデザイン事例
前述したとおり、AIは機械の目から見た情報をもとに判断し、表示することができます。
このようなAIの技術を活用したデザイン例をご紹介します。
The Next Rembrandt
こちらはレンブラントの作風をAIによって再現した作品です。
レンブラントは17世紀のオランダの画家です。
暗闇の中でスポットライトのような強い光線が一点に当てられて、その部分や暗闇の部分を強調するという明暗対比の技法がとられているのが作品の特徴。
代表作として「夜警」や「テュルプ博士の解剖学講義」が挙げられる、世界でも評価の高い画家としても有名です。
生涯において346作品をこの世に残しました。
レンブラントの死後から300年以上経った2016年に、マイクロソフトとオランダの金融機関のINGグループ、レンブラント博物館、そしてデルフト工科大学により、AIを活用してレンブラントの作風を再現するプロジェクトが組まれ、その作品が公開されました。
346あるレンブラントの作品全てをデジタルスキャンし、色使いやタッチ、レイアウトの特徴などをAIが解析したうえで、3Dプリンターを使って絵具の凹凸も再現しています。
このプロジェクトでAIは、向かって右側を向いた30~40代の、白い襟のある黒い服と黒い帽子の白人男性が、最もレンブラントらしい作品であると判断しました。
その条件のもと、多くの情報からデータを得て、今回の作品が作られました。
これはレンブラント作品のデータをもとにAIが作った作品ですが、「誰が見てもレンブラントが描いた油絵そのものである」と絶賛されています。
Edmond De Belamy
こちらはフランスを拠点にして活動しているObvious Artというグループが、AIを活用して作った絵画作品です。
2018年にニューヨークで著名オークション「クリスティーズ」において、43万2500ドル(約4860万円)という高値で落札されました。
この作品は、14世紀から20世紀に描かれた15,000点もの肖像画データをもとにアルゴリズムを生み出し、描かれたものです。
この手法を使ってできた作品は全11点。オークションで落札されたのは、そのうちの1点で、絵の右下にはアルゴリズムの数式がサイン代わりに入っています。
AIを活用して作った絵画がオークションに出品されるのは、この時が初めてだったため、当初の落札価格は7000~1万ドルと予想されていました。
しかし実際は予想の40倍以上の高値がつくという事態に。
この作品で用いられたアルゴリズムは、アーティストの間では何年も前から使われてきたものだったということもあり、AIの専門家や芸術家からは、オークションへの出品に対して批判的な声も上がったようです。
睡蓮 柳の反映
フランスの画家であるモネの代表作「睡蓮」。
そのうち、1916年に制作した「睡蓮、柳の反映」は、1921年にモネ自身が実業家の松方幸次郎に直接譲った作品です。
しかしながら、約60年間行方不明となり、2016年にパリのルーブル美術館にて上半分が失われた形で見つかりました。
作品が見つかってから、フランスと日本双方で記録を確認したところ、松方コレクションであることが確認されたため、松方家に返還となり、日本の国立西洋美術館に寄贈されました。
国立西洋美術館では、失われた部分をもとに戻すことはできませんでした。
そのため、作品の全図が映ったモノクロ写真や残った部分の化学的調査をもとに、使われている絵具の選定し、モネの描く手順や特徴などをAIに認識させることで、2019年にデジタルでの推定復元に成功しました。
国立西洋美術館によると、これほど大きく破損した作品は珍しく、通常であれば修復するのに2~3年はかかるとのこと。しかし今回は1年で修復が完了したそうです。
モナリザに命を吹き込む
ロシアのイノベーションセンター「スコルコボ」とサムスンの技術者たちが、AIを活用したアニメーション技術の開発に成功しました。
この開発の手法を使うことで、ある人物の静止画像が1枚あれば、その人物に命が吹き込まれ、あたかも話しているような動画を作成することができてしまうのです。
その人物が絵画であっても、この世にはもういない人であっても、作成することができます。
これまでにも、人間が表情豊かに話したりする技術はありましたが、同じ人物の表情に関する大量の情報を、AIが学習しなければなりませんでした。
しかし、今回開発された手法においては同じ人物でなくても、その人物の豊かな表情がリアルに動くよう、顔モデルを作り出すことができるのです。
この技術は映画産業やコンピュータゲームにおいて広く応用されることが期待されています。
AIが作るデザイン まとめ
AIは今回紹介した絵画や動画だけではなく、Webデザインにおいても進化しています。
非デザイナーであっても、AIを活用して開発されたWebサイトのデザイン作成やロゴ作成、そして自動彩色などのツールを活用することにより、より簡単にWebデザインを行うことができます。
AIのさらなる進化により、今後はより人間に寄り添ったデザインを行うAIが開発されるかもしれませんね。